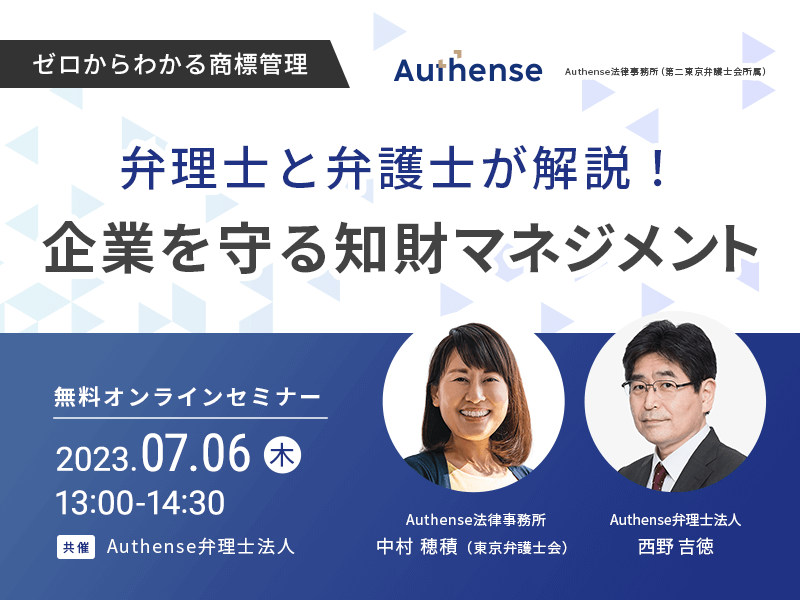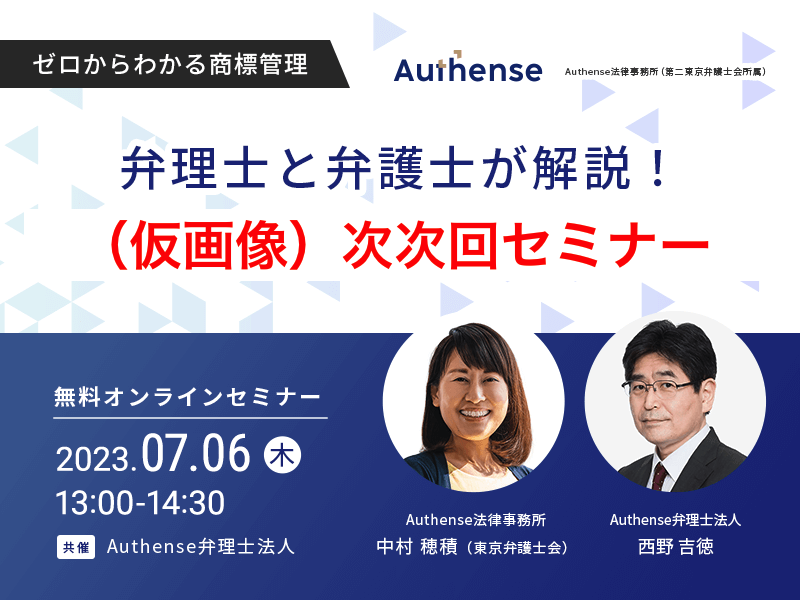人事評価制度の導入を検討する企業は、少なくありません。
では、人事評価制度とは、どのような制度なのでしょうか?
また、人事評価制度の導入は、どのように進めればよいのでしょうか?
今回は、人事評価制度の作り方や人事評価制度を導入するメリット・デメリットなどについて、社労士がくわしく解説します。
なお、当事務所(Authense社会保険労務士法人)は人事評価制度の導入支援に力を入れており、豊富なサポート実績を有しています。
人事評価制度の作り方でお困りの際は、Authense社会保険労務士法人までお気軽にご相談ください。
人事評価制度とは
人事評価制度は、個々の従業員の能力やスキルを適切に評価し、その評価を昇進や待遇に反映させる一連の仕組みです。
人事評価制度は所定のパッケージをそのまま採用して導入できるようなものではなく、自社に合わせて設計しなければなりません。
人事評価制度の導入をご検討の際は、Authense社会保険労務士法人へご相談ください。
人事評価制度の目的
人事評価制度は、どのような目的で導入されるのでしょうか?
ここでは、主な目的を4つ解説します。
企業理念や方針を社内に浸透させること
1つ目は、企業理念や方針を社内に浸透させることです。
人事評価制度の設計によっては、自社の企業理念や方針に沿った行動を評価する仕組みとすることが可能です。
企業理念や方針に沿った行動を評価対象とすることで、社内に企業理念や方針を浸透させやすくなります。
公平な処遇を実現しモチベーションを向上させること
2つ目は、公平な処遇を実現し、モチベーションを向上させることです。
人事評価制度がない場合、評価基準などが不明瞭となりやすく、従業員が「頑張っているのに評価されない」と感じたり、「自分は会社に貢献しているのに、ほとんど貢献していない同僚と同程度の給与であることに納得がいかない」と不満を抱えたりする場合があります。
人事評価制度を導入することで、公平感のある処遇を実現しやすくなり、モチベーションの向上につながる効果が期待できます。
自社に合った人材育成を行うこと
3つ目は、自社に合った人材育成を行うことです。
人事評価制度がない場合は社内でのキャリアパスが見えづらいため、人材育成も行き当たりばったりなものとなりがちです。
人事評価制度を導入することでキャリアパスが明確となるほか、自社が各ポストに相応しいと考える人物像も明確となることから、自社に合った効果的な人材育成が実現しやすくなります。
適材適所を実現すること
4つ目は、適材適所を実現することです。
人事評価制度がない場合は、各ポストに求める人物像があいまいとなり、人材のミスマッチが起きやすくなります。
人事評価制度を導入することで、各ポストの役割や必要なスキルが明確となり、適材適所を実現しやすくなります。
人事評価制度の主な種類
人事評価制度には、多くの種類があります。
これらは、「どれが優れている」などと一概にいえるものではありません。
企業の現状や将来展望、業種などによって適した制度は異なります。
ここでは、人事評価制度の主な種類について解説します。
なお、自社に合った的確な人事評価制度の導入をご検討の際は、Authense社会保険労務士法人へご相談ください。
業績評価制度
業績評価制度とは、従業員の業績を評価する手法です。
たとえば、売上高や新規顧客開拓数、生産量などが評価基準とされます。
目標値をトップダウンで定める「OKR(Objectives and Key Results)」のほか、目標値を従業員と上司とが共同で定める「MBO(Management by Objectives)」などが存在します。
能力評価制度
能力評価制度とは、従業員の業務遂行力やスキルなどを評価する手法です。
リーダーシップや提案力、コミュニケーション力など、企業が望ましいと考える能力が評価基準とされます。
行動評価制度
行動評価制度とは、企業理念に沿った従業員の行動や振る舞いなどを評価する手法です。
上司のほか、同僚や部下なども評価者とする「360度評価」が多く採用されています。
多面評価制度
多面評価制度とは、多角的な視点で従業員を評価する手法です。
たとえば、行動評価と業績評価など、複数の手法を組み合わせて評価します。
相対評価制度
相対評価制度とは、従業員間での位置づけによって評価する手法です。
たとえば、営業成績などをランク付けし、ランクが上位の従業員を高評価とする場合などがこれに該当します。
自己評価制度
自己評価制度とは、個々の従業員が自分の能力や業績などを自分で評価する手法です。
自己評価だけで評価を完結させるのではなく、他の評価手法と組み合わせて活用されることが一般的です。
人事評価制度の作り方
人事評価制度は、どのように作成・導入すればよいのでしょうか?
ここでは、人事評価制度の作り方について解説します。
- 自社の人事面での課題を洗い出す
- 人事評価制度の導入目的を定める
- 導入する評価制度を定める
- 評価項目と評価基準を定める
- 処遇・等級との関連付けを定める
- 評価者を教育する
- 社内に周知し運用を開始する
なお、自社だけで的確な人事評価制度を作り上げることは容易ではありません。
人事評価制度の導入をご検討の際は、Authense社会保険労務士法人までご相談ください。
自社の人事面での課題を洗い出す
人事評価制度はその導入自体が目的となるものではありません。
自社に何らかの課題があり、その課題を解決する手段の1つとして導入を検討すべきものです。
そのため、いきなり人事評価制度の設計から始めるのではなく、まずは自社の人事面での課題を洗い出すことから始めましょう。
人事評価制度の導入自体が目的となってしまうと、自社に合わない設計としてまったり、煩雑さに対してメリットが感じられない事態となったりするおそれがあります。
人事評価制度の導入目的を定める
人事面での課題を洗い出したら、その中から、人事評価制度の導入によって重点的に対処すべき課題を選定します。
これを人事評価制度の導入目的の中心に据え、制度設計を行うこととなります。
導入する評価制度を定める
人事評価制度を導入する目的が決まったら、その目的達成につながるか否かという観点から、導入する人事評価制度を検討します。
たとえば、導入目的が「経営理念を浸透させること」にある場合は、行動評価などが選択肢に入るでしょう。
同様に、導入目的が「営業部員のモチベーションを向上させる」ことにある場合は、業績評価制度などが有力な選択肢となります。
評価項目と評価基準を定める
導入する人事評価制度を定めたら、評価項目を定めます。
人事評価において重視すべき項目は企業によって異なるため、自社が重視したい項目を評価に反映させられるよう慎重に検討しなければなりません。
評価項目が定まったら、各評価項目について具体的な評価基準を定めます。
たとえば、能力評価において「リーダーシップ」を評価項目とする場合、何をもって「リーダーシップがある」とするのかの判断基準を定めるということです。
評価基準を明確にすることで評価者の主観が入りづらくなり、公平な人事評価を実現しやすくなります。
処遇・等級との関連付けを定める
続いて、人事評価と、処遇や等級との関連付けを定めます。
人事評価制度は単独で機能するものではなく、報酬などの処遇や昇進の基準となる等級と連動させることで、効力を発揮するものであるためです。
評価者を教育する
人事評価制度の全容が固まったら、制度の導入に先立って、評価者の教育を行います。
人事評価制度を適正に運営するには、評価者が制度の趣旨や評価項目、その意図などを正しく理解する必要があるためです。
評価者が制度を十分に理解せず、主観的な評価をする事態が横行してしまうと、人事評価制度は形骸化してしまうでしょう。
社内に周知し運用を開始する
導入に先立って、社内に人事評価制度を周知します。
人事評価制度の導入にあたっては、社内から不安や不満が呈されることが少なくありません。
従業員が「報酬の減額につながるのではないか」などと考え、疑心暗鬼となる可能性があるためです。
早期に不安を解決し、制度のスムーズの導入を実現するため、人事評価制度の目的を従業員に対して丁寧に説明し、理解を得るステップが必要となります。
人事評価制度を導入する主なメリット
人事評価制度の導入には、多くのメリットがあります。
ここでは、主なメリットを3つ解説します。
企業理念やビジョンが浸透しやすくなる
1つ目は、企業理念やビジョンが浸透しやすくなることです。
先ほど解説したように、人事評価制度の導入は企業理念の浸透に寄与します。
企業理念から「逆算」をして評価基準を定め、これを満たすことで評価される仕組みにすることで、従業員が自ずと企業理念を意識することになるためです。
従業員のモチベーション向上につながる
2つ目は、従業員のモチベーション向上につながることです。
人事評価制度を導入することで、公平な待遇を実現しやすくなります。
従業員が「頑張れば、その分だけ評価してもらえる」と感じることで、モチベーションアップにつながるでしょう。
また、キャリアパスが明確になることで「自分が、ほかに何を満たせば希望のポスト(等級)に就けるのか」がわかり、この点からもモチベーションの向上につながります。
効果的な人材育成が可能となる
3つ目は、効果的な人材育成が可能となることです。
人事評価制度を導入し、各ポスト(等級)の役割や求められる能力を定めることで、「4職級から5職級に上がるために何を満たすべきか」などの昇級基準も明確になります。
そのため、職級ごとに次の昇給に上がるために必要となる事項の重点的な育成・研修をすることが可能となり、効果的な人材育成が実現できます。
人事評価制度を導入する主なデメリット・注意点
人事評価制度の導入には、デメリットや注意点も存在します。
最後に、人事評価制度導入のデメリットと注意点を3つ解説します。
評価範囲外の業務が停滞するおそれがある
人事評価制度の設計方法によっては、評価対象外となる業務が停滞する可能性があります。
たとえば、相対評価制度や業績評価制度を導入してその評価基準を売上高のみとした場合、売上に直結しない業務に誰も手を付けなくなるリスクがあるでしょう。
その結果、職場内がギスギスし、退職者が増加するおそれも生じます。
導入や評価に手間がかかりやすい
人事評価制度の導入には、相当の手間がかかります。
人事評価制度の導入を成功させるには、自社に合った評価項目・評価基準を1つずつ検討する必要があり、他社の制度をそのまま流用することは避けるべきであるためです。
また、導入する評価制度の種類や内容によっては、評価者にも相当の手間が生じます。
「社労士に丸投げすれば、簡単に制度ができ上がる」というわけではないため、誤解のないようご注意ください。
ただし、社労士のサポートを受けることで、ステップごとに「自社が今、何を決めるべきか」が明確となるほか、事例を踏まえたアドバイスを受けることも可能となります。
人事評価制度の導入をご検討の際は、Authense社会保険労務士法人へご相談ください。
評価に納得感が得られなければ逆効果となるおそれがある
人事評価制度は本来、従業員のモチベーションアップに寄与すべきものです。
しかし、評価項目や評価基準に納得感が得られなければ、意図に反して、モチベーションの低下につながるおそれがあります。
そのような事態を避けるため、人事評価制度の設計は、自社の実情や将来展望などを踏まえて慎重に行わなければなりません。
まとめ
人事評価制度の概要や作り方、人事評価制度を導入するメリットや注意点などについて解説しました。
人事評価制度は、従業員の能力やスキルを適切に評価し、これを待遇などに反映させる仕組みです。
人事評価制度は決まったパッケージを採用したり、他社の規程をそのまま流用したりして導入できるようなものではありません。
自社に合った評価制度の枠組みを選定したうえで、自社の実情や理念、将来展望、業種などに応じて設計する必要があるものです。
人事評価制度の導入にあたっては、実績豊富な社労士のサポートを受けるとよいでしょう。
社労士のサポートを受けることで、自社に合った効果的な人事評価制度を設計しやすくなります。
Authense社会保険労務士法人は人事評価制度の導入支援を行っており、さまざまな規模・業種の企業への導入サポート実績があります。
人事評価制度の作り方でお悩みの際は、Authense社会保険労務士法人までお気軽にご相談ください。
お悩み・課題に合わせて最適なプランをご案内致します。お気軽にお問合せください。